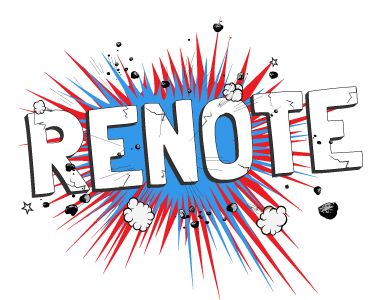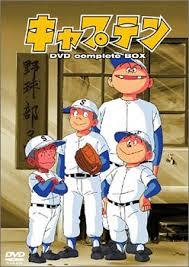野球が上手くなるための本&DVD50選【指導・食事メニューなど】

野球の魅力が書かれた本や指導書など、おすすめの本やDVD50選です。初級編、中級編、上級編とレベル別に分け、指導方法や食事法、日本や世界で活躍した選手たちの著書を紹介。サッカーやボクシングなど他のスポーツがテーマですが、野球にも応用できそうな内容が書かれた本も20冊載せています。

サッカーで子どもの力をひきだす オトナのおきて10(DVD付)
全国の保護者、指導者から絶大な支持を得る『サッカーで子どもをぐんぐん伸ばす11の魔法』の著者が子育て&コーチングの実践例をDVD映像とあわせて大公開。
既刊の池上さんの著書2冊も読みましたが、今回の新刊がベストです。大人(指導者)は何のためにコーチをしているのか? 子どもに何をしてあげたいのか?考えさせられる。ホントに子どものために指導しているのか?大人の欲求を子どもに押し付けてはいないか?読まなければいけない一冊。グラウンドに持っていくバッグにいつも入れておくべき一冊です。
出典: www.amazon.co.jp
文化としてサッカーを捉えていくと、行き着くところはピッチ上で繰り広げられているすべての営みの根本は「いかに人が育っていくか」という点にある気がしていて、そんななかで本書を読むと、このような指導者に巡り会えた子どもは幸せだなぁ、自分もこういう人にサッカーを教わりたかったなぁ、とつくづく思う。
サッカーの面白さは、「究極的には、プレーヤー個人の自由な判断に基づく動き」が交錯しあって、ボールという「目印」をもとに、「多様な人間関係のぶつかり合い」が展開されていくところにある。つまり、いくら監督の指示やチーム戦術が定まっていても、最終的には「自分の判断」で世界の見え方やとらえ方が決まっていく。
そうなると、サッカーを学ぶことは、そのまま「人生」を学ぶことと同義であり、「自分で考え、自分の力で表現・発信していく」というコミュニケーション基礎スキルを向上させていくことになる。なので池上さんの指導は、答えを言うのではなく「問いかけ」をコーチの側が発し続け、それを受け止めたプレーヤーが「自分で考え、自ら行動に移す」ことが重要となっていく。
出典: www.amazon.co.jp

子どもが自ら考えて行動する力を引き出す 魔法のサッカーコーチング ボトムアップ理論で自立心を養う
“教えない"指導が子どもを変える!
自主性を促す組織づくりで絶対につぶれない「人間力」を磨く
『個』と『組織力』をともに底上げする新理論
かつては無名だった進学校の広島観音高校を独自の指導で日本一へと導いた名将・畑喜美夫監督。
畑監督は選手が自ら考え、行動する「ボトムアップの組織論」を打ち出し、スタメンや戦術、メンバー交代までも
選手たちに決めさせるという指導法で全国に名前を知られる監督です。
指導者が選手にとことん教え込むトップダウンの指導は、体罰や暴力につながる可能性を秘めています。
選手が主体となるプレーヤーズファーストの指導が、いま求められる真の育成・教育ではないでしょうか。
最近、事業主となった私は、
これから人を雇う、育てるという立場にあります。
「最近の若者は…」といった声を周りからよく聞きますが、それは昔から、またこれからもずっと言われ続ける言葉なのでしょう。
そんな中で、そのように言われてしまう若者に対して、ダメだ、なっとらん、などと言うだけで終わってしまうことは非常にもったいない。
自身の成長の機会損失に繋がると思います。
その若者が悪いのではなく、その若者が過ごしてきた環境が悪かっただけで、なら新たによい環境をこちらが提供するべきで、もしそれで辞めてしまったのなら、それはその子のせいではなく、こちらに責任があったのだ。そう思える経営者でいたいと考えます。
出典: www.amazon.co.jp
サッカーのような創造的なスポーツは、トップダウンよりボトムアップの方がイイに決まっている。
が、わかっていてもできない。厳しい監督がいるチームにボロ負けすると「やっぱり子供には少し厳しいくらいがいいのでは?」と考えちゃうし、何べん言ってもわからない子供にはイラっとすることもある。そもそも、自主性に任せるととても時間がかかるのだ。
この人のすごいのはボトムアップをただ実践していることだけではない。ボトムアップを全国レベルの高校で実践していることだ。全国制覇を狙う高校でベンチ入りやレギュラーを子供に任せるなんて簡単にできることじゃない。試合中も子供の自主性に任せて指示をしない。例え、指示しない結果、負けたとしてもだ。
本田にしろ、俊輔にしろ、一流のプレーヤーは自問自答を繰り返している。一流とはいかなくてもサッカーを通じて教育をしようとするなら、子供が自ら考えるためにファシリテーターに徹することができるかどうか。少しでも教育に携わった人の方が、ファシリテーターであることの難しさを実感しているはずだ。
出典: www.amazon.co.jp

突破論
「どんなに素晴らしい理論や成功体験を持っていても、
選手一人ひとりの性格を見抜いた指導をしなげれば、
大舞台で結果が出せる選手には育てられない。
そして、その根底には信頼関係が必須だ」——。
平井ヘッドコーチの凄みは、北島選手を2大会連続メダリストに育てたことだけでなく、中村選手や寺川選手といった種目も性別も性格も違う人間を、世界で結果を出させた事。でも、本書を読み進めると、育てることが決して簡単ではないことが伝わってくる。可能性を広げて、現状を乗り越えるにはどんな考え方をすればいいのか、へーと思うような気づきが満載だった。
出典: www.amazon.co.jp
同じ著者の2008年の「見抜く力」に続いて読んだ。相手や状況に応じて指導法を変える、ゴールから逆算してシュミレーションする、選手に自分の泳ぎや状態を詳しく言葉で説明させることの重要性というような基本的な考えは同じだが、こちらの方が分量が多く、より新しい内容や経験が反映されている。例えば、人間性に対する要求についてはより柔軟性のある見解が述べられているし、既に経験や実績のある大人の選手を指導するときの方法の違い、惜しくも五輪直前に亡くなったダーレオーエンやロンドン五輪で金メダルを取ったキャメロン・ファンデルバーグを指導したことで気づいた日本人と外国人の違いについても述べている。チームとしての強化を図るときに中間レベルの選手や選考会で残れるかギリギリの選手の調子を上げるようにするというのも印象に残った。
出典: www.amazon.co.jp

10代スポーツ選手の栄養と食事―勝てるカラダをつくる!
成長期の注意点、ケガや減量中、試合前の食事など、アスリートに必用な栄養とレシピを目的別に紹介。
この本を参考に、かなり忠実に半年以上、中一になった息子に
食生活を実行しました。その後は都合により完璧とは言えませんが、
本人に食べる量や種類が身に付いたらしく、かなり近い食生活は送れています。
半年で162から167に背が伸びて(時期だったのかもしれないですが)、筋肉も
付いてきていますし、インフルエンザにもかからずに丈夫な体になってきました。
本人も本を読んで自覚したのも良かったようです。
出典: www.amazon.co.jp
スポーツのタイプ別に食事の取り方が開いているので 勉強になりました。大会当日の試合と食事の時間の計画なんかもあって 大変参考になります。実際 試合の日の食事は 取る時間にとても気を使いますから。いろんなパターンを考えて書いているので とても親切でわかりやすい実用的な内容でした。
出典: www.amazon.co.jp

基礎から学ぶ!スポーツ栄養学
進化するカラダは、何をどう食べるかで決まる!パフォーマンス向上に欠かせないスポーツ栄養学の基礎知識を、指導経験豊富な著者が完全網羅。スポーツ愛好者はもちろん、トップアスリートまで満足できるスポーツ栄養学の決定版。
正しい理解なくしては、真のパフォーマンス向上にはつながらない、そんな筆者の信念が軽快な文章からビシビシと伝わってくるような良著。
ありがちなアスリート向けレシピや食事のテクニックを紹介するのではなく、タイトル通り「栄養学」を「基礎から」しっかりと学ぶための本となっています。
とは言え、全編を通じて栄養学的な内容が全てスポーツの切り口で綴られていて、すぐにでも使ってみたくなるような話題が満載。
表面的なスポーツ栄養ではなく、そろそろ本気で栄養学をパフォーマンス向上に役立てたいアスリート、指導者には必携の一冊。
出典: www.amazon.co.jp
仕事仲間の管理栄養士から紹介され購入。
「誰が読んでも読みやすく、専門家が見てもなるほどと言うのが良書」
と以前聞いたが、この本はまさしくそんな本だと思う。
出典: www.amazon.co.jp

戦う身体をつくる アスリートの食事と栄養
スポーツ栄養の基本、それぞれの栄養素の働き、コンディション別の食事、具体的なレシピ等をわかりやすく、見やすく解説!少年期における注意点も充実。
毎ページに記載されている図が、イメージで理解しやすかったです。項目が短く要点がまとまってます。そのため、読むのに時間がかかりません。だからといって、内容が薄わけではありません。基本的なことはすべて記載されています。
出典: www.amazon.co.jp
料理を作り始めてからずっと疑問だったのは、
毎日なにを食べていたらいいのかということでした。
毎日食べたいものがあればいいんですけど、そういう食生活にも
飽きがくるので、基本パターンを作れればいいのですが、朝昼晩の型を紹介してくれる
本には出会えないできました。この本にはそれがあります。
出典: www.amazon.co.jp
アスリートたちの驚異的な食事メニューを紹介!大谷翔平は1日7食! - RENOTE [リノート]
renote.net
アスリートたちの食事メニューの内容や画像を集めました。強靭な身体を作るため、一般人では考えられない食事量を摂取しているのです。野球の大谷翔平やダルビッシュ有、プロレスラーの中西学など、彼らの驚異的な食事メニューを紹介していきます。