オニオン・グラタン・スープのイロハ

寒いなー、冬だなー、パリのテロニュースが流れたなー。
そんなことを連想していたら、ある雑誌に載っていたオニオングラタンスープのことを思いだしました。料理名から察するに、スープ状のタマネギグラタンを予想していましたが、調べた結果、半分アタリで半分ハズレのようです。
しょうがありません。だって、パリに行ったことがなければ、そのスープを実際に味わったこともないのだから。
『ku:nel』が紹介したオニオン・スープ

『vol17 ku:nel パリのすみっこ案内。』
発行所:マガジンハウス
「ストーリーのあるモノと暮らし」をテーマにした雑誌『ku:nel』。特集によって、買ったり買わなかったりしますが、テーマどおり、一つひとつの企画が読み物的で、時間をかけて愉しめます。読んだあとも捨てることなく、とっておいて、気がむいたときに再読するという―ようは、わたしと相性がいい雑誌です。
2006年1月発行の『ku:nel』では、巻頭に堀内誠一氏が描いたパリの人びとを散りばめて、パリ取材の様子を掲載しています。いくつかのトピックを読みすすめたところに、「オニオングラタンスープは夜食の王様。」という記事があるのです。
パリ生活30年という佐藤真さんが、ご自身のスープ初体験や家庭で作るオニオン・スープのことを書いています。ほかにも、壇一雄著『壇流クッキング』の一文、レストランの支配人とのエピソードも載せていて、是が非でもスープを一口すすってみたくなる内容です。
2ページの記事のなかで写真は3点。
ギャルソンが給仕したとき(だろうな)、こんがり焼けたチーズを食べたとき(だろうな。中身がちらりと見えるように)、そして、なんくちかお腹に収めたあと(だろうな)。うーん、卵色のスープのなかにバゲットやチーズの残りが見えている!アツアツで、濃厚そうで、嫌う人は絶対にいないはずのスープの写真に、一人で熱狂してしまいました。
もっともっと知りたくなる、魅惑のオニオン・グラタン・スープ!
玉村豊男がスープを語ると…
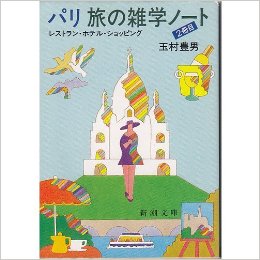
『パリ旅の雑学ノート 2冊目』
著:玉村豊男
発行所:新潮文庫
玉村豊男氏といえば、食にうるさいというか、一家言もっているという印象ですよね。こちらの文庫は、著者ならではの視点でパリのレストラン、ホテル、ショッピングの詳細が書かれています。文庫は1978年、それ以前に単行本が1973年に出版されているとのこと。
どこでオニオン・グラタン・スープが登場するかというと、トピック「メニューの解読法」。店頭に置かれた手書きメニュー(もちろんフランス語)を攻略するという内容で、パリ中央市場のレストラン「グラン・コントワール」に「昔ながらの市場名物オニオン・グラタン・スープ」の(翻訳)表記があるというのです。
前述の佐藤さんのスープ初体験のときの記述にも中央市場のくだりがありました。市場で働く人たちが、仕事前や休み時間の夜食だった、とあります。
玉村さんのトピックに、「スープの食べかた、またはマナーについて」というのもあって、そこでは「スープは食べるもの」として説明されています。
スープsoupeという言葉はもともと、パンを肉汁や牛乳などに浸して食べる場合にそのパン切れのほうを指した言葉で、それがのちに、パンやらいろいろな具をぶちこんだいわゆる“スープ”自身のほうを指すようになった。だから、その名残りで今日でもスープは“飲む”といわず“食べる”というわけだが―
―p96より引用
手書きのメニューから、さらに玉村さんが走り書きした日本語表記を読んでいると、寒空の下で料理をえらぶパリジェンヌになったような気分になります。「冬場は生ガキが名物 6コまたは12コ単位で注文するのがならわし」とか、「このブロックが前菜 18~25フラン程度」だとか。メニューの翻訳だけでなく、パリの息づかいというか、そこで暮らす人々の雰囲気がつかめるのもいいですよ。
さらに時代を遡って、石井好子がスープを語ると…

『パリ仕込みお料理ノート』
著:石井好子
発行所:文春文庫
もっと時代を遡ると、シャンソン歌手として活躍した石井好子さんのエッセイ集から、オニオン・グラタン・スープを発見しました。こちらは文庫が1983年、単行本が1970年の出版とのこと。
パリでの暮らしや料理について、いくつものエッセイを集めていて、そのなかに「悲しいときにもおいしいスープ」という一話があります。悲しいというのはオニオン・グラタン・スープのことではないので、そちらは無視して大丈夫です。
レストランでオニオングラタンを注文する方はたいへん多い。グラタン皿の中でまだぐつぐつ煮えているオニオングラタン。茶色に柔らかく煮えた玉ねぎスープの上に、パンと、とろっと焼けてとけたチーズがのっているのを、スプーンでくずしながら食べる味は格別だ。
―p26より引用
1970年代には、日本には欧米文化が流れこみ、洋食が身近なものになってきたころ。けれど、実際にパリで暮らす石井さんのエッセイは女性たちの憧れだったにちがいありません。エッセイに落とし込まれた素敵な言葉を一つひとつひろって、その料理をイメージした人も多かったはずです。
パリのキャフェでは、大どんぶりで焼いた煮立っているのを持って来て、別のスープ皿にざっとあけてくれる。フォークとスプーンを使って食べるのは、グルュイエール・チーズがまるでチューインガムのようにのびるからだ。
“グラティネ”といえば、フランス人の夜食にはかかせぬものなのに、フランスのオニオングラタンはあまり日本人向きではない。分量が多すぎるし、チーズもたっぷりで、チューインガムのようにのびるチーズと戦っているうちに、いやになってしまうのだ。
―p26より引用
いえいえ、石井さん。わたしは食べたいですよ、オニオン・グラタン・スープを。分量が多かろうと、チーズがガムのようにのびようと、北風が吹きつけるこの季節、パリジェンヌのようにふーふーと口元をとがらせて味わいたいものです。

